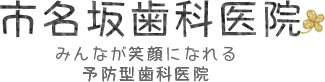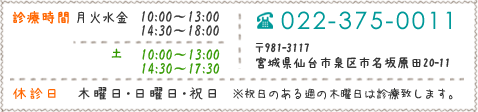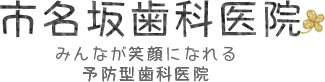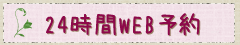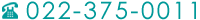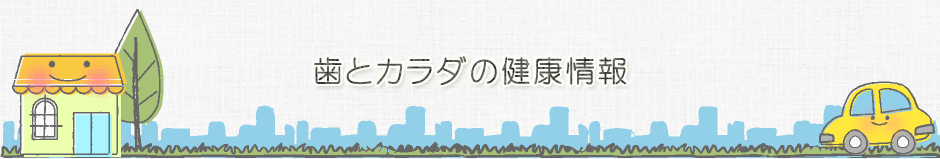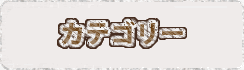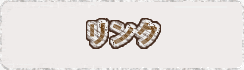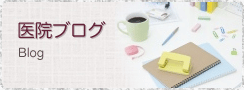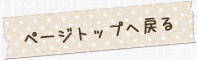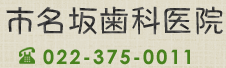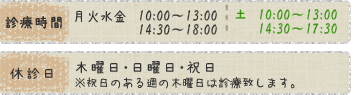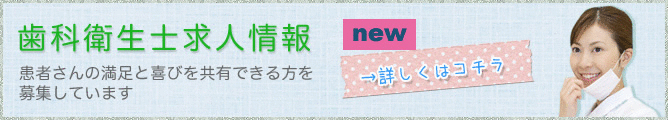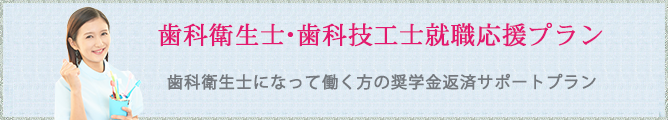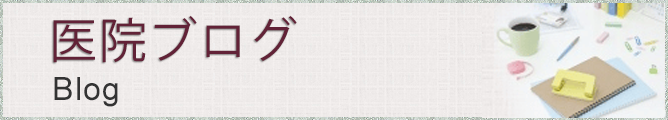認知症になりたくなければ歯を守りましょう(33)
脳の老化を防ぐ歯のケア方法・・・・・・その8
・他にもある!「咬む」ことがもたらす8つの効果
(1)がんや生活習慣病の予防
唾液には、発がん性物質が作り出す活性酸素を消す作用がある「ペルオキシダーゼ」が含まれているため、咀嚼回数を増やして唾液の分泌を促すことで、がん予防効果が期待できます。
他にも、脳卒中や心筋梗塞、動脈硬化、糖尿病、骨粗鬆症などの予防にも有効だと言われています。
(2)免疫力アップ
咬むことで副交感神経を刺激します。
白血球中のリンパ球をコントロールする働きのある副交感神経を優位にすることにより、リンパ球を増やして免疫力を高めます。
(3)アレルギー性の病気予防
未消化のまま腸管に届いた食べ物が抗原となり、アレルギーを発症することがあります。
食べ物をしっかり咬んで、唾液とよく混ぜて消化することで、抗体の反応を抑えることができ、食物アレルギー、アトピー性皮膚炎、花粉症などの予防にも効果があると考えられています。
(4)口臭予防
咬むことで唾液の分泌が促進されます。
唾液には、口腔内細菌を抑制する効果があるので、細菌が発生させる口臭も抑えることが可能です。
(5)ダイエット効果
よく咬むことで味覚が刺激されると、交感神経を高めるホルモンの「ノルアドレナリン」が分泌されます。
その結果、全身の細胞の働きが活発になって代謝がよくなり、太りにくい身体になります。
(6)シワ予防効果
よく咬む動作により、口の周りの筋肉が鍛えられるので、シワやたるみを予防する効果も期待できます。
(7)幸福度アップ効果
幸せホルモンである「セロトニン」は咀嚼することでも分泌されます。
咀嚼回数を増やすことで、ストレス緩和効果やリラックス効果が期待できます。
(8)人付き合い円満効果
セロトニンは、人に共感する脳の働きにも関わりが深く、咀嚼回数を増やしてセロトニンを分泌させることで、人付き合いや恋愛もうまくいく可能性が高くなります。