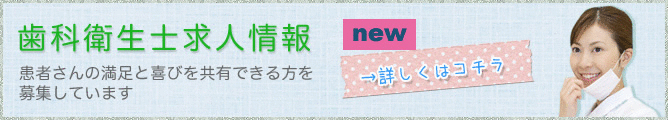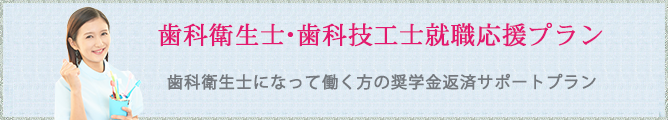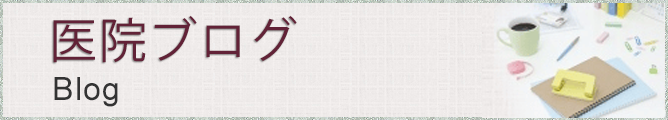歯周病がアルツハイマー病の進行を促進!?
歯周病と全身疾患の関係について、糖尿病のことは何度かお伝えしてきました。
今回は歯周病治療が、アルツハイマー病の進行を遅らせる可能性もあることについて考えてみたいと思います。
認知症のなかで最も多い、アルツハイマー型認知症は、脳の萎縮が特徴のアルツハイマー病によって起こる認知症のことです。症状は物忘れなどの記憶障害や判断力の低下などです。
歯周病との因果関係については、まだわかっていないことも多いですが、動物実験の結果は、歯周病がアルツハイマー病を悪化させる原因の一つであることがわかりました。
人工的にアルツハイマー病にしたマウスの半数に歯周病を発症させたところ、歯周病のないマウスよりも認知機能が悪化。実験後に、脳に沈着したアルツハイマー病の原因とされるたんぱく質(アミロイドβ)を調べると、歯周病のないマウスに比べて、歯周病のあるマウスのものは重量で約1・5倍、面積では約2・5倍になるそうです。
お口の中の歯周病菌や炎症のもととなる物質などが、血流に乗って脳に運ばれ何らかの影響を与えているのではないかと考えられています。
歯周病がアルツハイマー病を悪化させる原因ならば、歯周病の治療はアルツハイマー病の進行を遅らせる有効な手段になりうるかもしれません。
歯周病で歯を失うことも、アルツハイマー病と無関係ではありません。
アルツハイマー型認知症の発症には脳の神経伝達物質の減少が関わっていると考えられています。神経伝達物質は噛むことによる刺激が脳に伝わることで増えるからです。また、噛むことが脳を活性化することもわかっています。つまり、歯周病によって歯を失うことが、アルツハイマー型認知症の引き金にもなりかねないということなのです。
残存歯数とアルツハイマー型認知症の関係
平均年齢70歳後半の残存歯平均
*アルツハイマー型認知症の人(36人)・・・3本
*脳血管性認知症の人(39人)・・・6本
*健康な高齢者(78人)・・・9本
アルツハイマー型認知症の人は健康な人よりも歯の本数が少なく、また、残っている歯が少ないほど脳の萎縮が進んでいたと言うことが報告されています。
では、歯を失わないようにするためには、歯周菌を予防していくことが大切です。
歯周菌が急に多くなる原因は免疫力の強さが20代をピークに下降していきます。
その発症と進行に生活習慣が深く関わってきます。40歳を過ぎる頃、免疫力が弱くなり歯周病菌が勢力を強めていくことになります。
重度の歯周病に進行してしまうと歯を失う原因になるので、早めに歯周病対策をすることが、認知症の予防にもつながります。


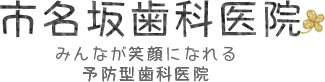
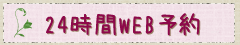
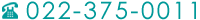
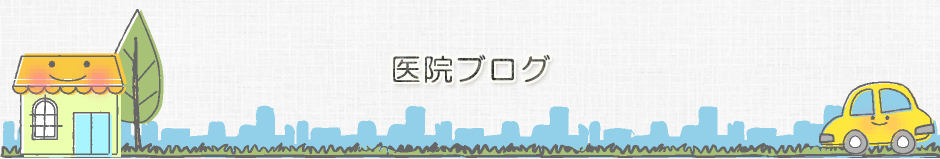

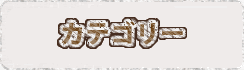
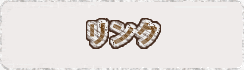


.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)